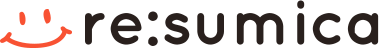茶道師範でもある作庭家の高橋良仁さんが手掛けた自宅の茶庭(露地)は、住宅街の一角とは思えない、静寂な空気が流れる異空間。茶道になじみのない人も心を奪われる、伝統的な美意識が詰まった癒やしの茶庭を拝見しました。

作庭家の高橋良仁さんは、17年前、埼玉県北浦和の住宅街に自宅を建てたとき、本格的な茶室を設けました。その際、140㎡程のスペースに茶庭(別称:露地)も作り、ご本人の茶名瑞鳳庵宗仁にちなんで“瑞鳳庵”と名付けたそう。ご自身の設計、施工による茶庭は、丁寧な技術に独創的なセンスを織り交ぜた、一貫性のあるくつろぎの和空間として評判となり、時折海外から訪れる人もいるんだとか。

腰掛けの背面側がリビングになっている高橋家。石積みの遮断効果で、窓からの眺めもどこか浮世離れした趣が素敵でした。
「茶室で客人をもてなす茶事を催す際に、なくてはならないのが茶庭です。一連の所作を、あうんの呼吸で進めるのが茶事のたしなみですが、物言わぬ時間を過ごすからこそ、細部の作りがいっそう大切な役割を果たします」(有限会社庭良代表取締役 高橋さん・以下同)。別世界のオーラを放つ茶庭の中身を、見せていただきました。
目次
木漏れ日と風が心地いい
客人の待機スペース「腰掛待合」は
踏み石ひとつにも意味やこだわりが

茶庭を進むと中門手前に円座が置かれた腰掛が登場。客は部屋で身支度をし、季節のお湯などをいただいた後、庭へ移動します。
「腰掛待合は、客が静かに座って景観を楽しみながら、亭主が出迎えにくるのを待つスペースなので、居心地の良さも必要です」。長年かけて各地から集めているという石は、形や色、配置など、高橋さんのセンスとこだわりが感じられる、見た目のバランスがいい作りに。実際に座ってみて驚いたのは、一般の住宅の庭にいるとは思えない心地よさ。まるで古寺を訪れたようなすがすがしさを覚えました。
- 足元に並ぶ踏み石は、客が座る場所の目印として設置されたもの。立場順に奥から主客石、次客石、連客石と呼ばれます。
- 実際の茶事で待機中の皆さん。腰掛にあるレトロな喫煙道具の煙草盆は、懐石料理の合間などに出されるそう。(画像提供:高橋さん)
住宅になじむようアレンジされた「中門」
苔に埋もれた飛び石が風情を呼びます

飛び石は着物の歩幅に合う間隔で配置。対面であいさつをする際(迎え付けのご挨拶)、全員の顔が見えるよう、縦一直線に並べずあえて横にずらすのもお作法。
茶事の際、ご亭主は、頃合いを見計らいながら中門に出て“腰掛”で待つ客と初めて顔を合わせます。「露地(茶庭)は中門を境に、内露地と外露地に分けられています。中門は比較的作り手の好みが反映されることが多く、こちらも屋根が湾曲になったオリジナルバージョン。苔が後から自然に生えました」。完成から時を経るごとに飛び石が苔に埋もれていき、中門ともあいまって、いっそう風情のある景観へと変化していくところも見どころ。
- 大きな亭主石が見える中門より奥を内露地、客石が並ぶ手前を外露地と、名称が変わるのだとか。
- あいさつ風景。この日は高橋さんのお仲間がご亭主役。かがみこみながら無言で。(画像提供:高橋さん)
- 中門脇には夜の茶事に使う照明用の石燈籠はがあります。外露地の適切な場所を選んで設置されます。
50種類以上ある素朴な山採りの樹木を
効果的に「植栽」したことで
年月を経てより表情豊かな庭へ進化

趣向に富んだ植栽と苔が根付いた木曽石が見せる美しい風景。「味わいのある山採りの木と優しい印象を持つシダや苔など、表情豊かな植物を選びました」。
植栽には特に決まりがなく、美術のような感覚で自由に作り上げていったという高橋さん。「最初に選んだのは、山採りをメインにした50種類ぐらいの木々。後から加えた植物も育ち、最初に見越していた通り、バランスよく木漏れ日が入るように」。秋になると紅葉がひときわ美しい高橋邸。手をかけなくても自然に味わいが増していくのが、日本の庭が持つ魅力です。
- オオスギゴケ、地苔のコツボゴケなど数種類が繁茂。「苔同士せめぎあいながら、好条件の場所を選び広がっていきます」
- 茶庭の突き当たりは、日本建築の技術が集約された土塀で幕を。素朴な山採りの木とあいまって、古式ゆかしい風景に。
古来の決まりに沿って作られた「躙口(にじりぐち)」。
軒で庭と建物をつなぎ一体感のある庭に

内露地に入ったら、手を清め、世俗の思いを捨てる所作を。その後、左手に見える躙口(にじりぐち)から茶室へ入り、茶事が始まります。
壁に取り付けられた引き戸が、躙口(にじりぐち)と呼ばれる茶室への入り口。にじって入りやすいよう、亭主の膝の位置を目安に設計されているのだとか。「躙口(にじりぐち)の寸法や形、作りにはある程度決まりがあり、それに習って作りました。庭と建物をつなぐ軒内は日本建築の特徴的な部分。茶庭に一体感を出す役割を担っています」
- 腰をかがめて入る様は、茶庭ならではの非日常感たっぷり。茶室の中は薄暗く、ひんやりした空気が。
- 塵穴とは、それぞれが持つ日常の立場や世俗を捨てて茶室に入る、といった意味合いを持つ場所。
- 布泉型の蹲踞(つくばい)と、泥で仕上げた鉢明かり。神社のちょうず鉢や灯籠が由来だそう。
◆名庭〈瑞鳳庵露地〉はこうして誕生◆
- 17年前の高橋邸建設予定地。隣家が面している側に茶庭は作られました。(画像提供:高橋さん)
- 回りの風景を遮断するために、塀代わりの石を積み上げる作業からスタート。(画像提供:高橋さん)
- 石積で周りを囲い終わると、入り口の中門や茶室側の軒内など、茶庭の内部に着手。(画像提供:高橋さん)
- 時間の経過とともに、緑が深くなりいっそう趣を増した現在の〈瑞鳳庵露地〉。(画像提供:高橋さん)
この場所は、「借景」に頼れない新興住宅地。茶庭に求められるのは、あたかも山の中にいるような静寂さなので手腕が問われるところ。「隣接する家を含めた近隣の景色を視界から取り除き、周囲とは異質な空気感を作ることを意識しました」。具体的には、背景に石を積み上げることで周りから遮断された空間を作り上げました。約3カ月かけて茶庭が完成し、「瑞穂庵露地」と命名。「17年前より木々が大きくなって地苔も増えたので、庭に新たな広がりが見えてきました。そんな成長を見るのも楽しみのひとつです」
・・・・・・・・
細かなルールと自由発想の部分、その両方があるからこそ、伝統的ながら独創的な空間を作ることができた高橋邸の茶庭。戸建てに住んでいても、ここまで立派な庭はなかなか作ることができませんが、もしこれから自宅に庭をと考え中なら、日本庭園や茶庭の決まり事を少し意識してみると、個性的でありつつ落ち着きのある空間が手に入るかもしれません。
(撮影/相澤琢磨)
取材したのはこちら

今回茶庭を見せていただいた、作庭家の高橋良仁さんは、庭の設計施工管理を自社で行う作庭事務所の代表。露地など伝統的な技法により自然素材を活かした庭作りや近代建築にも合う庭作りも行う。常に自然と人の関係を思考し、現代の「日本の庭」を模索しながら作庭しています。現場ではいつも厳しい職人の顔を持ちながら、普段は優しいおじいさま。「古いものが珍しいのか、孫が遊びにくると楽しそうに茶庭で遊んでいます」と目を細める一面も。